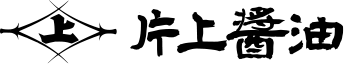木桶で発酵熟成した
醤油本来の芳醇な味わい。
木桶醤油は、ワインやウイスキーを樽の中で熟成させるのと同じく、 木桶による醤油本来の製法にこだわったプレミアムな醤油です。 醤油は和食の心臓部であり、 土台となるもの。 その味を支えてきた木桶醬油は 日本全体で1%未満、 現存する木製の醸造桶はわずか3000から4000個と言われています。
弊店では、製造する醤油の全量を大きな杉の木桶に仕込みます。
深さ2メートル弱、直径は容量によって異なりますが、弊店では大体1,5メートル前後のものが多いです。
木桶は仕込み、醗酵容器として古くから使われてきたものですが、現在主流のFRPやステンレスの大型醗酵タンクと比べて依然として優れている点があります。
木桶で造る
Make in wooden barrel

究極の醗酵容器
木桶は容量が異なっても、深さ(高さ)は大体同じに作られています。これは木桶の容量が変わっても空気に触れている面積との比率が変わらないことを意味します。約2メートルの深さが、容量と空気に触れる面積の比率を醗酵容器として優れたものにしています。先人の知恵は凄いと思います。
醗酵とは無酸素状態での微生物の営みを指すことが多いですが、醤油のように高濃度の仕込では僅かに溶存酸素がある諸味表面付近でしか醗酵出来ません。この2メートル弱の深さですと木桶に棲みついている菌が自然に繁殖して旺盛に醗酵します。それに対し、背の高い大型の醗酵タンクでは、棲みつきの菌がいないため、培養装置で菌を培養して加えないと発酵しません。このような人為的な管理がないと醗酵しない仕組みは、発酵工業として均一なものを大量に作るには優れています。一方、木桶による発酵は多種多彩な微生物がせめぎ合っておきる複雑な醗酵を人の熱意と感覚でより良い方に持っていくという「醸造」のロマンにあふれています。
木桶は成長する


最も安心できる材質であること、持続可能な取り組み。
木桶は吉野杉でできています。樹脂や金属のタンクが危険なわけではありませんが、やはり木の器、木桶が一番安心できる材質、材料と思います。奈良県吉野郡の吉野杉、住宅の建材としても使われますが、そもそも桶材として植林、育林されてきました。吉野の急峻な岩山で育つ木は成長が遅く、その分木目が詰まっているので、優秀な桶材となります。吉野独特の密植と間伐、枝打ちを繰り返す技術、桶用に特化した木取り、製材の技術も相まって、吉野は国内各地へ一級の桶材を供給してきた歴史があります。
良い桶材とは桶になったときに漏れない、滲まない木材です。それには側板の断面を木目が途切れることなくきちんと横断していることが大事なのです。大きな桶は半径が大きいので、木目のカーブも大きくあってほしいのです。木目が詰まっていてほしいのに、太い木が欲しい、そのために100年以上の木を使う必要があります。杉は通常50年から80年ほどで伐採されますが、吉野の山では百年二百年の木が立っています。「孫や曾孫のために」なんて言いますが、いやいや5代6代後の子孫のために木を植え、育ててきた方々の努力の上に木桶が出来上がっています。
100年以上の木を使ってできた新桶は醤油屋、味噌屋では塩分のおかげで100年以上もちます。江戸時代製造で200歳現役という木桶もあるそうです。今、100歳の木桶は都合200年以上前に誰かが植えた木で作られています。そして今作った新桶が役目を終えるのは100年後200年後です。
来年、来月のこともどうなるかわからない現代ですが、この木桶の100年単位の話、夢とロマンにあふれていると思いませんか?そして100年の心意気が詰まった木桶が育てた醤油を楽しんでいただければ幸いです。
木桶製作の話
The Story of Wooden Barrel Production




絶滅の危機からの再出発
現在、日本で稼働している木桶の多くは戦前につくられたもの。長く新桶がつくられない時代が続き、職人もほぼ消滅状態でした。2012年、ヤマロク醤油の五代目・山本康夫の呼びかけから「木桶職人復活プロジェクト」が始動。食品メーカーや流通業者、大工、料理人などが毎年1月に小豆島に集い、新桶づくりに取り組んでいます。
2013年にわずか10人で始まったこの取り組みは、今では600人規模にまで拡大。その中には海外からの参加者も増え、2024年は20組を超えるエントリーがありました。また、渋谷ヒカリエでのトークイベントや阪神百貨店での催事なども開催され、木桶の可能性を一般消費者へも伝える場となっています。
新しい桶、新しいつながり
木桶醤油を伝えて、木桶醤油を使いたいという人を増やす。その結果として、木桶が増えて、さらには、木桶をつくる職人が増えていく。そんな循環を目指して、木桶仕込みをしているメーカーが連携しています。本来であれば競合にあたる面々。小豆島に集まり、同じ方向を向けるというのは、共に大工仕事をして、大宴会をして、という時間を共有しているが故だと感じています。
奪い合いではなく、広げ合う
流通量わずか1%の市場を、奪い合うのではなく、皆で2%へと育てていく。今では、醤油メーカー60社以上が参加し、木桶醤油の市場そのものを大きくしようと活動しています。足の引っ張り合いの競争ではなく、品質の高めあいで競争をしようという雰囲気が醸されています。これらの取り組みは、2023年には「古典の日文化基金賞」も受賞しました。
※本稿は(職人醤油 醤油の知識 木桶醤油の概要)からの引用・参照によるものです。